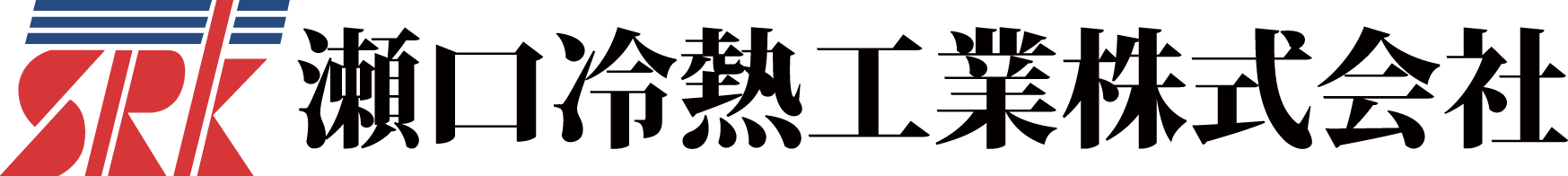今回は空調設備の洗浄・清掃について紹介します。
まずは室外機の中の熱交換器の洗浄です。室外機の熱交換器は汚れが付着しやすい箇所にあり、汚れたまま放置しますと熱交換がうまくできなくなってしまいます。
最悪の場合はエアコンが停止、故障してしまう事もあるので、繁忙期の前に必ずチェックし、汚れていたら洗浄する様にして下さい。
次に室内機の洗浄です。室内機の種類は、壁掛け、天カセ形、天吊形、床置形が一般的です。
熱交換器と送風機の汚れにより、室内機の能力が低下します。
また、汚れやカビ等を放置すると室内の空気環境を悪化させます。
空調機の維持管理の為にも定期的に空調機洗浄が必要です。
次は空調ダクトの清掃です。空調機の汚れ・カビ等により空調ダクト内部は汚れています。
空調ダクト内部に溜まった汚れは運転時の風により、飛散して吹出口より室内に吹き出す可能性があり、そのまま放置した場合は室内環境を悪化させます。10年~15年に1回はに空調ダクト清掃が必要です。
最後に厨房排気ダクトの内部清掃についてです。厨房排気ダクトは油汚れが付着しやすく、ダクト内部に火が入り込んだ場合は火災のリスクを伴うこともあります。
1年~2年に1回の清掃をお勧めします。
これらを実施していくことで、電気代の節約、長期使用が可能となります。